過去問を解いていると、「この問題の答えは
確かコレだったな」と、回答を覚えてしまう
ことってありませんか?
過去問は何度も解くことが大事といいますが、
単純に答えを覚えてしまったから回答できて
いるのであれば意味がありません。
過去問の正当率がたとえ9割を越えていた
としても、『回答を覚えていただけ』であれば
正しい実力は測れません。
「自分は余裕で合格点をとれる!」
そう思って本番の試験に挑んだのに
全然問題が解けなかったら残念ですよね。
『過去問が解ける=理解できている』と
勘違いしないように、ここでは過去問を
有効に活用する方法をお伝えします。

過去問の活用方法
過去問の選び方
過去問の勉強方法の前に、まずはどの過去問を
選ぶべきかということをお伝えします。
過去問題集の選択でミスをしてしまうと、
勉強の効率が大幅に下がってしまうので
注意してください。
過去問は必ず1問1答形式のものを選びましょう。
1問1答形式の過去問とは、過去の試験問題が
そのまま載っているものではなく、それぞれの
選択肢が独立していて、その文章が正しいか
誤っているかを判断する形式のものです。
試験形式の場合、正答であるものが明らかで
あれば、他の選択肢の理解が曖昧であっても
正しい選択肢を選ぶことができます。
しかしそれでは、理解が曖昧なものばかりの
選択肢となった場合に、正答を選ぶことが
難しくなってしまいます。
実際の試験で、過去の試験と似たような
問題が出たのに正答できないのであれば
非常にもったいないです。
よって、一つ一つの選択肢をしっかりと
理解できるように、1問1答形式の過去問を
選ぶことは外せません。

過去問の進め方
まずは過去問を解いていってみましょう。
このとき、
しっかり理解できていて正答できれば「〇」
間違えたり、分からなかったら「×」
なんとなく理解しているなら「△」
というように、問題文の頭のところに
印を入れておきます。
過去問の2周目も、同じように1つ目の印の
右隣に印を入れていきます。
3周目以降は、2つ「〇」がそろった問題は
とばして、間違えたり、理解が曖昧だったもの
だけを解いていくようにします。
こうすることで、自分が理解できていない
部分が明白になっていくので、理解できるまで
重点的に勉強します。
試験までに弱点を克服しておきましょう!

まとめ
過去問を何度も解いているうちに、答えを
覚えてしまって、『自分は本当に理解できて
いるのかな』と心配になるかもしれません。
しかし『答えを覚えること』の意味合いは
試験形式の問題と1問1答形式の問題とで
大きく異なります。
試験形式の問題は『どれが正解か』を覚える
ことになりますが、1問1答形式の問題は
『この文は正しいか、どこが誤っているか』を
覚えることになります。
つまり、実際の試験で選択肢が入れ替えて
出題されても、正しい選択肢を選べるように
なるということです。
まずは勉強するのに最適な過去問題集を選び、
何度も繰り返し過去問を解くことで
社労士試験合格を目指しましょう!
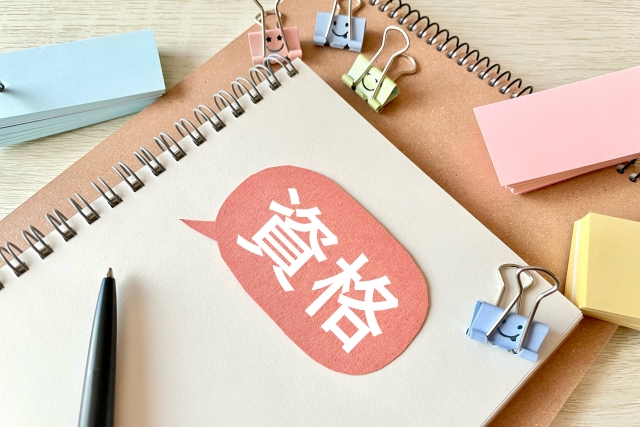


コメント